短期前払費用には要注意!こんな支払は一括経費にならない
記事作成日 2020/10/14 記事更新日 2023/02/05

1.短期前払費用とは?適用要件、趣旨など
法人税基本通達2−2−14に、前払費用の額は、当該事業年度終了の損金の額に算入されないものとされています。つまり、通常、前払費用として計上したものは、翌事業年度に役務提供されるため、当該事業年度の損金に算入されません。ただし、前払費用でも例外として損金として算入できるケースが、同じ通達に記載されています。先述の文章の後半に記載されています。
法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している時は認められるとされています。
この規定には注書があり、収益の計上と対応させる必要があるものについては認められないとされています。ここで前払費用を損金として算入される要件は以下の5つあります。
- 支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること
- 提供を受ける役務に対して対価を支払っていること
- 継続的に行われる取引で同様の方法で支払っていること
- 継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること
- 収益の計上と対応させる必要がないもの
なお、当該の通達の趣旨は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるということになっています。
要するに、会計処理で重要性がなくて簡便的な処理が認められるものを税務でも同様に損金として認めてあげるというものです。
2.適用されない前払費用もある
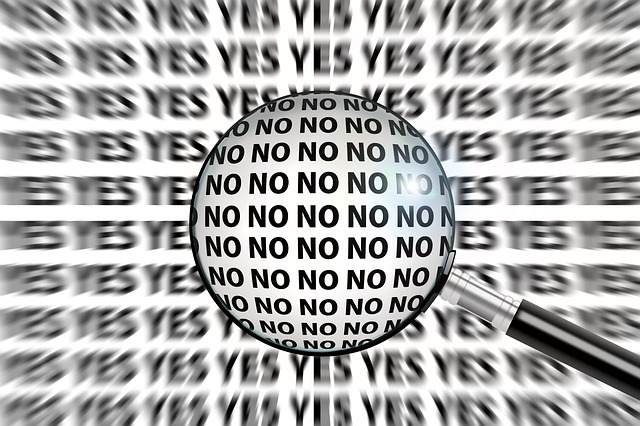
ここまで短期前払費用が損金として算入される要件、算入される趣旨などについてみてきました。算入される要件があるということは、算入ができないものもあるということになります。基本的には先述した要件に一つでも該当しなければ損金にできません。
では、以下の例は短期前払費用として適用できるでしょうか。
- 建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)を2月末に前払により支払う。
- 建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)を3月末に前払により支払う。
- 建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃月額を毎月末に前払により支払う。
- 1年契約の倉庫賃借に係る賃料について、家賃年額(4月から翌年3月)を3月末に前払により支払う。
- 賃貸している建物について建物を賃借しており、当該賃料について、
毎年、家賃年額(4月から翌年3月)を3月末に前払により支払う。
答えはbとcが短期前払費用の例外が適用できます。ということで、それぞれの例についてみていきましょう。
aですが、どの要件が引っかかって適用することができないのでしょうか。それは2月末に年額の家賃を支払っている点です。2月に支払い、翌年の3月まで役務提供を受けるため、①の要件の支払った日から1年以内に提供を受けるという点が満たしていません。
bとcですが、これは短期前払費用の例外を満たしているのですが、ある前提が成り立っているから、適用要件を満たしているとしました。その前提とはどういう前提でしょうか。
それは要件のうち、③の継続的に同様の方法で処理されているという前提です。家賃なので毎年支払っているものですが、役務提供にあわせて損金算入しているにもかかわらず、ある年だけ前払費用を損金に算入することはできません。
利益が出たから、ある年だけ前払費用を損金に入れると課税が適切に行われないため、認められません。
dですが、これはどの要件が引っかかるかというと、毎期継続的に同様の方法をとる必要がありますが、単年の契約のため、継続的な処理ができないため、短期前払費用の例外は適用できません。
短期前払費用の例外ですが、継続的に同様の処理が必要であるため、複数年契約で決まる家賃などは適用されやすいですが、複数年契約できないものは適用できません。
eですが、これは⑤の収益の計上と対応させる必要がある点が満たしていません。これまでみていた家賃とは異なり、建物を賃貸して収益を獲得しており、当該収益に家賃を対応させる必要があります。よって、短期前払費用の例外処理は適用することができません。
3.まとめ
短期前払費用は通常損金処理をすることはできません。ただし、例外として会計上の重要性、及び、継続的に適用することを前提にして
短期前払費用を損金に計上することができます。つまり、継続的に同じ処理ができない費用は適用できません。
また、収益に対応する費用などは適用できません。性質的に適用できない経費もあるので留意しましょう。
最後に、注意しておきたいのが、節税効果を狙って適用したとしても、継続的に同じ処理がなされることが必要であるため、初年度のみしか節税効果は出ません。こういう費用が適用できるのか興味や疑問をお持ちになったら、ご相談ください。
利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら
安全に税金対策をしたい方へ
税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。
もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。
それは、「節税に強い専門家」に相談することです。
弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。
なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。






