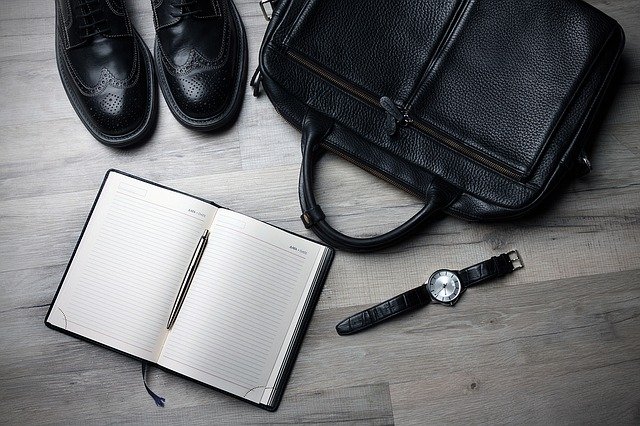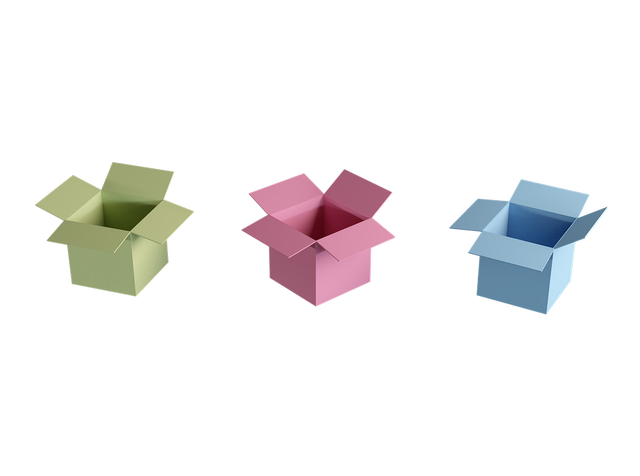必ず行っておくべき節税10選!!
記事作成日 2020/10/18 記事更新日 2023/02/05

はじめに
節税を考える上で、まず、「節税」「脱税」の違いを理解しましょう。
「節税」は法人税法等の税法上の範囲内で、法律が認める方法で無駄な税金を払わないようにすることが目的です。一方で、「脱税」は法律の規定を破り、法を犯して税金を払わないようにすることであり、「節税」と「脱税」は、全く違うということをご理解してください。次に、節税する上で性質に応じて、4つのカテゴリーに分類します。
| 保険 | 王道 |
| 消費 | 投資 |
今から説明するのは、王道(表の右上)の節税方法⑩選になります。
必ず行っておくべき節税10選
①「旅費規程」を活用して節税
「旅費規程」とは、社員が出張などで外出した際の旅費や交通費などの実費精算や日当等について定めた規程のことを言います。当該規定を用いることによって、支払った側である会社側は「会社の経費」となります。
また、ここで重要な点は受け取った側である社長及び従業員側も「税金の対象外」ということです。つまり、所得税や住民税の対象外になります。「旅費規程」を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
②「役員社宅」を活用して節税
「社宅」とは福利厚生の一環として、会社側で用意する住宅のことです。この社宅は会社で住宅をいったん契約し役員や従業員に住まわせた場合は、「会社が事業を行うにあたり必要不可欠である従業員の雇用のために家賃を支払っている」とみなされ、会社の経費になります。
「役員社宅」を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
③「役員報酬を適正化」を活用して節税
「役員報酬」とは会社の役員に支払われる報酬です。「役員報酬」を適正な金額に設定することは法人税のみならず、個人の所得税・住民税にも影響してきます。
つまり、役員報酬の金額を増やすと法人の税金が少なくなりますが、個人の所得税・住民税の税金は増えます。一方で役員報酬の金額が少なくすると、法人の税金が増え、個人の所得税・住民税の税金が少なります。
このように役員報酬は法人の税金・個人の税金にも影響してくるため、適正な金額を設定し、法人税・所得税・住民税の最適化を考える必要があります。「役員報酬を適正化」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
④「短期前払費用」の特例を活用して節税
短期前払費用の特例を活用すれば、一定の要件を満たす費用について、本来資産計上すべき費用を当期の経費として算入することができ、節税につなげることができます。「前払費用」とは、一定の契約の下、継続的に等質・等量のサービスを受ける場合に、まだそのサービスが提供されていないにも関わらず、支払いをした費用のことです。
そのうち、支払日から1年以内にそのサービスの提供を受けるものを「短期前払費用」といいます。例えば、保険料、賃借料等が該当します。しかし、活用するには条件もございますので、「短期前払費用」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
⑤「消耗品費」を活用して節税
消耗品費は、基本的に10万円未満の物品を購入するための費用です。文房具、日用雑貨、オフィス備品のような主に事務・作業に使用する備品であれば対象となります。
10万円未満の消耗品費については、使用時に経費となります。そのため、10万円未満の会社で使用するパソコン等は使用することで、その期の経費とすることができます。「消耗品費」を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してください。
⑥「少額減価償却資産」の特例を活用して節税
「少額減価償却資産」とは取得価格が30万円未満の減価償却資産のことをいいます。
つまり、⑤で述べた、消耗品費の取得価格が10万円未満を超えている場合にも、取得価格が30万円未満の場合、その年の損金(≒経費)として計上することができます。しかし、活用するには条件もございますので、「少額減価償却資産」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
⑦「中古車」の特例を活用して節税
自動車のような高額な物を購買した際は、購入額は通常分割されて複数年にわたり計上されます。これを減価償却と呼びます。購買したものによって耐用年数が定められており、この耐用年数にわたって購入額を償却していくこととなります。
この耐用年数が新車の場合と中古車の場合とで考え方が異なっており、経過年数4年の中古車の場合、耐用年数は2年となります。定率法で減価償却する場合、耐用年数2年の中古車は初年の償却率が100%となります。そのため、4年落ち以降の中古車は1年目で購入金額の全てを経費にすることが可能なのです。「中古車」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
⑧「貸倒引当金」の特例を活用して節税
貸倒引当金とは、将来発生するかもしれない貸し倒れに備えて、あらかじめ一定額を計上しておく科目のことです。
例えば取引先へ商品を販売した際、その場で売上金をやり取りせず、後から請求書等を通じて支払を行うことがあります。この支払を待っている期間、その支払は売掛金と呼ばれます。
しかし、取引先の倒産等により売掛金が回収できなくなることがあり、これを貸し倒れといいます。そのため、この貸し倒れのリスクに備えてあらかじめ一定額を損失として計上しておく際に「貸倒引当金」という科目を使用します。
貸倒引当金は経費算入できるため、計上すれば節税に繋がります。「貸倒引当金」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
⑨「決算期変更」の特例を活用して節税
全ての法人は、会社の経営・財務状況を、一定の期間を区切って決算する必要があります。この「一定の期間」を事業年度といい、1年以内であれば何ヶ月で設定しても問題ありません。
また一般にこの事業年度の最終日を「決算日」、決算日が含まれる月を「決算期」と呼んでいます。期中、とくに期の終盤に突発的な利益が出た場合、そのまま決算日を迎えると法人税等の税金が通常よりも多くかかってしまいます。そんなときは事業年度を短縮することにより、利益を翌期に持ち越し節税をすることが可能です。
「決算期変更」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
⑩「棚卸資産の評価方法の見直し」の特例を活用して節税
棚卸資産とは一般に「在庫」のことを指します。企業や個人事業主が販売を目的として一時的に保管しているものを棚卸資産と呼びます。
税金は利益に対してかかってくるため、利益が少なくなればそれだけ支払う税金も少なくなります。利益は、売上高-売上原価-経費で計算されるため、売上原価や経費が大きくなればその分利益が圧縮されることとなります。
また、売上原価=期首の棚卸高+当期の仕入高-期末の棚卸高、期末の棚卸高=個々の棚卸資産の期末評価額×個々の棚卸資産の数量の総和でそれぞれ計算されます。そのため、棚卸資産の期末評価額が下がれば、期末の棚卸高が減り売上原価が大きくなるため、利益が圧縮される=節税につながるということです。
「棚卸資産の評価方法の見直し」の特例を活用した節税の詳細についてはこちらを参照してくだい。
ここでアイスブレイクを挟みましょう。ここでは、絶対やってはいけない節税3選もご紹介しましょう。
絶対やってはいけない節税3選

①「架空経費」の計上
「架空経費」とは、本来、経費の取引が発生していないのにも関わらず、実際取引があったように、経費として計上することです。
この行為は冒頭に述べたように、「脱税」行為にあたりますので、「脱税」行為で有罪になった場合、科される刑罰は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。さらに国税通則法違反処分に加えて附帯税、いわゆる追加徴税も支払う必要があります。
②「不必要な消費」による経費計上(表の左下)
事業拡大をする上で、手元現金預金つまりフリーキャッシュフローを残すことはとても重要なことになります。フリーキャッシュフローは、あくまで税金も考慮した後、いくら残っているかになります。
つまり、事業の拡大に結び付かない無駄な経費等を使用していると、最終的なフリーキャッシュフローが残らず、いざ事業規模を拡大するタイミングがきても、投資ができないことになり、それは会社経営をする上で本末転倒な結果といえるでしょう。
③「売上隠し」による税金逃れ
「売上隠し」とは、本体計上すべき売上の取引が発生したのにも関わらず、会計上その取引を計上しないことを言います。このような行為も「架空経費」で述べたように、「脱税」行為にあたります。
次に、王道による節税をしてもなお、税金をおさえたいという方に投資による節税について説明しましょう。
投資による節税4選(表の右下)
①「LED投資事業」による節税
LEDはLight Emitting Diodeの略で、発光ダイオードのことです。このLEDを利用して各種照明に役立てるものがLED照明です。
LED照明の1本あたりの単価は、だいたい1本あたり4,000円です。そして、1本あたりの取得金額が10万円未満の場合は消耗品費となり、購入金額を経費処理することによって、その全額を利益から控除することが出来ます。このLED投資事業について、詳細はこちらを参照してください。
②「ドローン投資事業」による節税
ドローンはエンターテイメントとしてはもちろん、不動産の計量測定や災害時の物資配達、撮影などさまざまな場面で活躍が期待されています。但し、ドローンを使用するために資格が必要であり、昨今ではドローンスクールが急速に広がってきており、生徒数もかなりの増加となっています。
このスクールで使うドローンの1機体あたりの金額は税込で約9万円です。そして、1機あたりの取得金額が10万円未満の場合は、購入金額を経費処理することによって、その全額を利益から控除することが出来ます。
③「エアコン投資事業」による節税
エアコンのレンタル需要は不動産オーナーの方から、非常に高まってきております。このレンタルで使用するエアコンの1台あたりの金額は10万円未満です。そして、1台あたりの取得金額が10万円未満の場合は、購入金額を経費処理することによって、その全額を利益から控除することが出来ます。
このエアコン投資事業について、詳細はこちらを参照してください。
④「中古ヘリコプター投資事業」による節税
航空機、ヘリコプターなど、固定資産の減価償却期間は法令によって定められており、個人や企業が勝手に変更することはできません。新機のヘリコプターの場合は「5年」が減価償却期間となっています。ただし、中古ヘリコプターの場合は償却期間が「1~2年」となります。償却期間が1年となれば、購入した年度に全額を経費に充てることが可能です。
この中古ヘリコプター投資事業について、詳細はこちらを参照してください。
利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら
安全に税金対策をしたい方へ
税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。
もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。
それは、「節税に強い専門家」に相談することです。
弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。
なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。